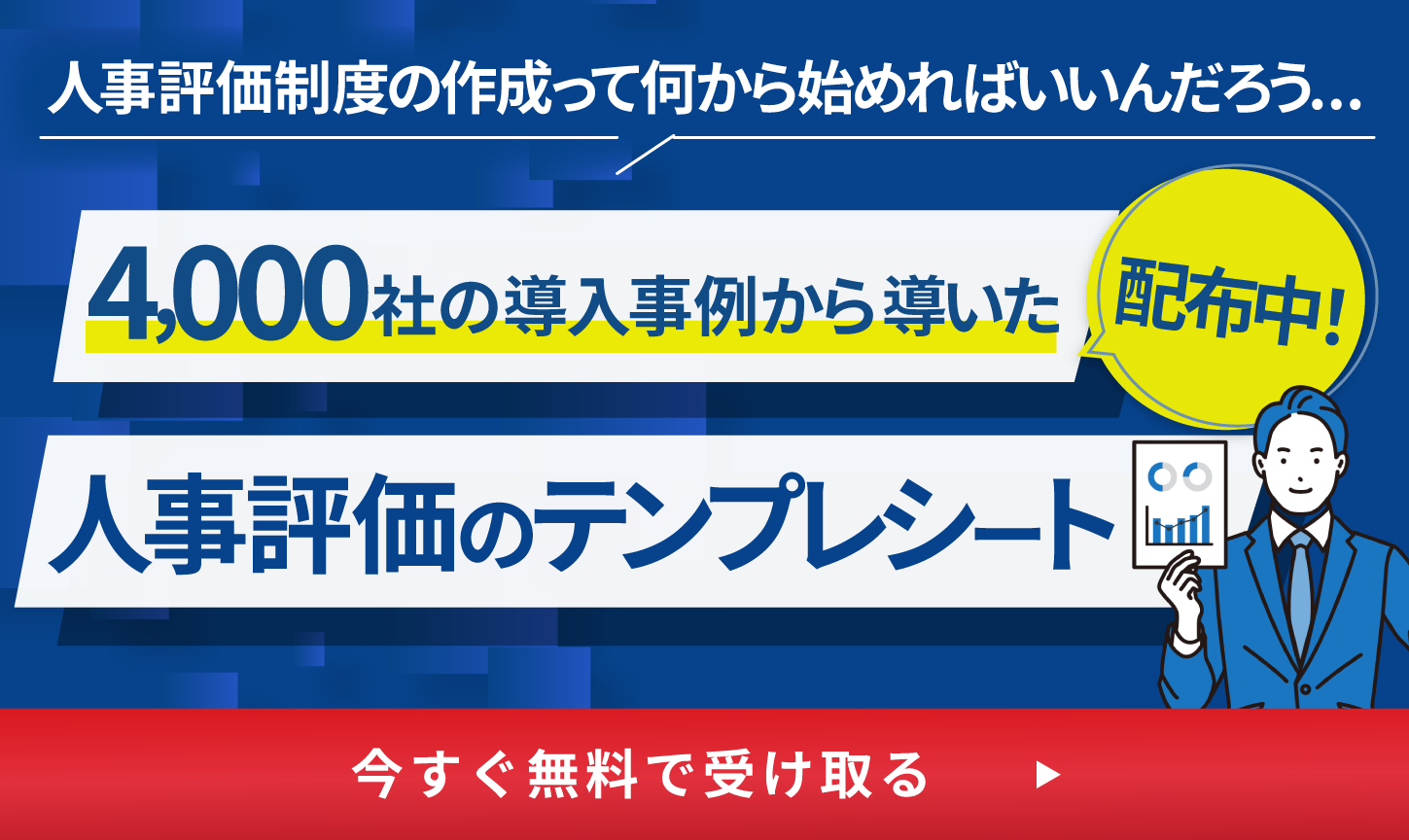ビジネスシーンにおいて、Will-Can-Mustの考え方を理解し、キャリアを構築していくことは重要です。
「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(やらなければならないこと)」 の3つの要素から成り立ちます。
この3つの要素をビジネスシーンに置き換えると以下のような考え方ができます。
- Will:仕事の目標
- Can:業務に活かせるスキルや知識
- Must:やるべき業務や責任、周囲から求められていること
will-can-mustは仕事のモチベーション向上やキャリア構築に欠かせない要素です。本記事では、will-can-mustについての理解を深めると同時に、目標設定や活用方法についても解説します。
ぜひ、組織の活性化に役立ててください。
目次
will-can-mustとは?

will-can-mustとは、ビジネスにおいてモチベーションを維持したり成果を出しやすくしたりするためのフレームワークです。別の表現をすると「やりがいを持って仕事をするために必要な要素」になります。
従来、仕事は上からの指示を受けて行うトップダウンの方式が多く見られました。しかし、年功序列や終身雇用が崩壊した現状では、定期的な昇給や昇格は望めず、老後の年金生活に不安を覚える人も少なくありません。
長い下積みを経てある程度の年齢で管理職へ昇格し、多額の退職金を得て優雅な年金生活を送ることがモチベーションとなっていた人にとっては、厳しい実情です。
そこで必要になるのが仕事のやりがいや満足感です。will-can-mustの考え方は、3つの輪が重なり合うところに仕事の満足感が生まれ、重なりが大きいほど満足感が高くなる考え方です。
そうはいうものの、このようなフレームワークをひとりで実行するのは限界があります。will-can-mustも、ひとりよりもグループで行うほうが効果的です。
ここからは、will、can、must、それぞれの意味や必要とされる理由を解説します。
- Will
- Can
- Must
意味を理解すると、wil-can-mustの本質を理解できるようになるでしょう。
Will(やりたいこと)
Willが意味するものは「希望」です。ビジネスにおいては「何を実現したいか」であり、動機や欲求、志など、働く目的に直結するものでもあります。
たとえば、ある人物がビジネスドラマを見て「このドラマに出ている主人公のような仕事ができる人になりたい」と思うのがWillです。
次に「仕事ができる人になったら信頼できる仲間を増やしたい」「いずれはその仲間と起業したい」など、次々とやりたいことが見えてくるでしょう。
これらはすべて、今、目の前にある仕事をするためのモチベーションにつながります。仕事は、目的や目標があるからできます。もちろん、自分のWillを達成するためにはいくつものハードルがあるかもしれません。
先の例で考えるのなら「仕事ができる人は元からオーラがある」「いい人だけれど本当に信頼できるか見極められない」「起業には当然リスクが伴う」などです。
しかし、これらのできない理由を考え始めるとキリがありません。なぜなら、状況は刻々と変化するものだからです。
大きな自然災害が起きれば計画通りに物事は進まなくなり、結婚や出産のライフイベントが訪れることもあります。Willを考える際には、状況やリスクは抜きにして純粋に何がやりたいかを考えましょう。
Can(できること)
Canが意味するものは「強み」です。人はみんな、それぞれ異なる強みを持っています。どんなに自分は平凡な人だと思っていても強みはあるものです。
強みは大きく2つに分かれます。1つは、専門的な知識や技術など、特定の業種で活かせるもの。もう1つは、コミュニケーション能力の高さや他人への思いやりなど、業種や職種、企業を問わずに生かせるものです。もちろん、どちらの強みも持つ人もいるでしょう。
自分に何ができるかわからない人は、入試や就職試験の面接を思い出してみましょう。
「あなたの長所と短所を教えてください」という質問に返した答えが、当時から変わらない自分の強みです。「短所は優柔不断なこと」と答えていても、協調性や傾聴力という言葉に変えるだけで強みになります。
自分のCanを考えることは自分を知ることです。たとえば「500円のコーヒーと3000万円の家、自分はどちらが顧客に売りやすいか」と考えたとき、意外にも3000万円の家を売るほうができそうだと考える人は少なくありません。
これは、500円のコーヒーを売れる人は接客スキルが、3000万円の家を売れる人は営業スキルが高いことを意味します。
このように、Canを知るということは自分にはどのような仕事が向いているのかを考えるきっかけにもなります。
Must(自分の役割)
Mustが意味するものは「使命」です。WillやCanは、あくまでも自分を主軸として考えるのに対して、Mustはその逆です。自分が周囲から何を求められているのか、何をやるべきなのかを客観的な視点から見てみましょう。
Mustが必要な理由は、自分がやりたいことと周囲の期待がずれていないか確認するためです。
たとえば「1000万円の売上をあげる」という目標を、自分も周囲も共有していたとします。しかし、自分は500万円を2件獲得したいと思っているのに対し、周囲は250万円を4件獲得してほしいと思っていることがあります。
500万円を支払う顧客は、その後も企業に利益をもたらす上顧客になるかもしれません。上顧客の獲得は、営業として満足度が高いです。
一方、企業側はその後の戦略として、低価格帯の商品を主軸にしようとしており、利益を出すためにはより多くの顧客を獲得する必要があると考えます。
このように、数値的な到達点が同じでも目的に対する認識が異なると、自分が想像したよりも低い評価になってしまうこともあります。Mustを考える際には、自分がやりたいことはさておき、周囲が自分に求めていることを冷静に判断しましょう。
will-can-mustはリクルートで取り入れられている
株式会社リクルートでは、従業員育成のために「Will Can Mustシート」を活用しています。従業員は半年に一度、以下の項目についてシートへの記入が義務付けられています。
- Will:本人が実現したいこと
- Can:生かしたい強みや克服したい課題
- Must:業務目標や能力開発につながるミッション
これにより、一人ひとりの個性を生かし、やりたいことを目標に結びつけられると考えられています。シートをもとに上司とすり合わせを行い、そのうえで何をすべきかを決定していくため、モチベーションを持って仕事に臨めます。
will-can-mustのフレームワークとは?
will-can-mustのフレームワークは、就職活動やキャリア形成など目標設定における様々なシーンで活用されています。will-can-must、それぞれの意味は以下の通りです。
- Will:したいこと、やりたいこと
- Can:できること
- Must:しなければいけないこと
目標設定をする際には、これらの3つの要素がバランスよく含まれている必要があります。
例えば、Willの要素が強く、Mustの要素が弱い目標設定をしたとしましょう。自分のやりたいことのために目標を立てることは決して悪いことではないものの、組織や企業にとっては不要なものであれば意味がありません。
また、逆も同じです。組織や企業にとって必要であっても、本人ができないことやしたいことでない場合にはモチベーションが維持できず達成への道のりは困難と言えるでしょう。このような観点から、目標設定にはwill-can-mustが非常に重要なのです。
では続いて、will-can-mustひとつひとつの要素を深掘りして見ていきます。
Will
まずWillは、「やりたいこと」や「夢」、「目標」などが挙げられます。
本人の目指したい将来像やこれからやっていきたいことなどがWillに当てはまります。「起業する」「課長に昇進する」という具体的なものもあれば、「顧客満足度の高い営業になる」といった抽象的なものまで様々です。
ポイントとなるのは、自分自身の意思です。本人が心の底から、やりたい、目指したいと思えているかどうかは非常に重要と言えるでしょう。
もちろんここでのWillは、必ずしも業務に直結している必要はありません。Willを洗い出していく際には、まず大まかで良いので本人のやりたいことや好きなことなどを聞き出しましょう。
今は明確化していなくても、好きなことややっていて楽しいことを整理することでどんどんWillが固まってくるでしょう。
Can
Canは、「できること」です。たとえWillの要件を満たした目標であっても、現実的に実現不可能であれば意味がありません。
例えば社会人で休日に野球をしている男性がプロ野球選手を目指すのはほぼほぼ不可能と言えます。
目標設定において大切なことは「達成可能かどうか」ということです。達成できない目標を立て実行したとしても、達成が難しければモチベーションは維持できません。
とはいえ、実現が簡単すぎるものも企業としても成長が見込めず、意味のなさない目標となってしまいます。そのため、目標達成の際には本人が達成可能なラインを意識しましょう。
Must
Mustは、「しなければいけないこと」です。
具体的には組織や企業から求められている項目で、使命・義務・責任などという言葉にも当てはめられるでしょう。
例えば、自社の社員がエンジニアとして活躍するための目標を立てたとします。しかし、その社員は企業には営業社員としての活躍を期待されていれば、その目標は企業や組織にとってはプラスになりません。
WillとCanを満たした目標であっても、Must の要件を満たせていなければ組織・企業の成長にはつながらないのです。そのため、目標設定を行うためには企業にどのような影響を与えるのかも意識しながら設定していきましょう。
しかし、Mustの要素が大きすぎると社員のモチベーション維持が難しくなるため、バランスが大切です。
will-can-mustのフレームワークを活用するメリット

【従業員に対する価値】
従業員にとっては、自己理解が深まり、チームの一員としてできること、するべきことを明確に把握できるようになります。
お互いのwill-can-mustを理解し合いながら仕事を進めることで、モチベーションが向上し、チームパフォーマンスも上がります。
メンバー間の相互理解が深まることで、チームの方向性が定まり、ひとりでは成し遂げられない目標も、チームで協力して達成できる可能性も高まるでしょう。
will-can-mustのフレームワークでは、グループ学習や研究集会などチーム内でのコミュニケーションを活発にする取り組みが行われます。この取り組みによって、お互いの理解がより一層深まり、チームとしての力を最大限に発揮することが可能になります。
【経営・人事に対する価値】
一方、企業にとっても、will-can-mustのフレームワークは大きなメリットをもたらします。
チームに所属する個人が自分について深く知り、チームの一員としての役割を明確に把握することで、チームの方向性が定まり、パフォーマンスが向上します。
will-can-mustのフレームワークの活用は、チームの力を最大限に発揮できるようにします。
また、異動や昇格等を含めた人事制度にwill-can-mustのフレームワークを導入することで、従業員のモチベーションや目指す将来像などを明確に把握でき、それに合わせた施策を打ち出せるでしょう。
加えて、従業員のモチベーションや目指す将来像などを客観的に把握することで、適材適所の人員配置が可能になり、組織全体の生産性向上や従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。
社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。
その評価制度で社員は満足してますか?
全国4,000社の導入実績から導き出した
あしたのチーム式人事評価シートはこちら>>
社員側へのメリット
will-can-mustのフレームワークを活用することで、社員自身の「やりたいこと」や「できること」、「すべきこと」が明確になり、キャリア形成における目標設定が容易になります。
チーム内で互いのwill-can-mustを共有することも効果的です。社員同士の協力体制が築きやすくなり、個人では達成困難な目標も、皆で協力して達成できる可能性があります。
また、自身の強みや課題を客観的に把握できるため、スキルアップや自己成長に繋げやすくなるでしょう。日々の業務においても、自身の役割を意識することで、主体的に行動できるようになり、モチベーション向上にも繋がります。
企業側へのメリット
will-can-mustのフレームワークを導入することで、従業員の個性や強みを把握でき、人員配置も適切に行えます。さらに、従業員のキャリア目標を把握することで、モチベーションの向上や離職率低下にも繋がるでしょう。
また、人事評価制度にwill-can-mustの要素を取り入れることで、従業員の成長を促し、組織全体の活性化にも貢献できます。研修や1on1ミーティング等の機会を通じて、従業員と企業側が相互理解を深めることで、より効果的な人材育成や組織運営が実現できます。
will-can-mustを考えるタイミング
will-can-mustのフレームワークは、キャリア形成や自己理解を深める上で非常に有効なツールです。
自身の役割や、環境が変化するタイミングでwill-can-mustのフレームワークを活用することにより、効率良く自己分析や目標設定が行えます。具体的には、以下のとおりです。
- 役職が変わる時
- 転職する時
- キャリアを見直す時
- 面接の時
これらのタイミングでwill-can-mustを考えることで、自身の現状を整理し、将来を見据えた上で「今後どういった行動をすべきか」が明確になります。
ここでは、will-can-mustを考えるタイミングを解説します。
役職が変わる時
新しい役職に就く際には、これまでとは異なる役割や責任が求められます。
まずは以下のwill-can-mustを考えていきましょう。
- やりたいこと(will)
- できること(can)
- 果たすべきこと(must)
また、新しい役職での自身の成長目標や課題を明確にすることで、具体的な行動計画を立てることができます。目標や課題が明確になることで、社内でのコミュニケーションも取りやすくなるでしょう。
転職する時
転職は、自身のキャリアを大きく見直す機会です。will-can-mustを活用することで、転職先に求めることや、自身の強みを明確にし、後悔のない選択ができるようになります。
たとえば面接の際、企業に対して自分自身のプレゼンを行うことで、入社後に活躍できるイメージを持ってもらいやすいです。将来のキャリアプランと照らし合わせながら、転職の目的を明確にすることも重要です。
キャリアを見直すとき
定期的に自身のキャリアを見直すことは、長期的な成長に不可欠です。will-can-mustを考えることで、現在の状況と将来の目標とのギャップを把握し、具体的な行動計画を立てることができます。
キャリアについて悩みがあり、新しいことに挑戦したい時など、現状を打破したい場合に特に有効です。自身のwill-can-mustを定期的に確認し、柔軟にキャリアプランを修正していくことが大切です。
面接の時
面接では、自身の強みやキャリアプランを明確に伝える必要があります。
will-can-mustを事前に整理しておくことで、自信を持って自己PRができます。企業側とのミスマッチを防ぐためにも有効です。また、面接官からの質問に対して、具体的なエピソードや根拠を交えて答えることができるため、説得力が増します。
企業が求める人物像と、自分自身のwill-can-mustを照らし合わせ、入社後のキャリアイメージを具体的に描けるでしょう。
will-can-mustを活用した目標設定の方法
will-can-mustの要素を理解したら、早速目標を決めていきます。will-can-mustを活用した目標設定の方法について見ていきましょう。
Willを考える
まずは、Willを考えていきます。Willは、自分自身の興味や関心、そして他人への憧れなどから考えていきます。Willがわからないという場合、まずは自身の過去を振り返っていきましょう。
過去の行動や言動の中で、自分自身が「楽しい」「面白い」と感じられることを探します。
充実感や楽しいと思うことに対して、なぜなのかと深堀していきましょう。そうすることで、自分にとってのポジティブな感情が明確になります。このような方法で、自分自身のWillを考えていきましょう。
Canを考える
Canでは自分自身にできることを明確にしていきましょう。
これまでやってきた仕事や得意なことを明確にしていきます。例えば営業であれば、交渉力や新規開拓のためのテレアポや飛び込みなどが挙げられます。
事務であれば、ワードやエクセルなどの事務スキルなども挙げられるでしょう。ただ職種という大枠だけではなく、具体的にどんな仕事ができるのかを洗い出していきましょう。
また、Canは実務的なスキルだけではなく、粘り強さや継続力といった内面的な自分自身の強みなども含まれます。自分自身で見つからない場合には客観的に判断するのも一つの手です。
「ストレングスファインダー」などを活用すれば自分でも気づけていない強みが分かるかも知れません。
Mustを考える
続いて、Mustの要件を考えていきます。属している企業や組織にとって必要なことや、それらをより成長させるために欠かせないものなどを考えていきましょう。
Mustを考える際、人事担当として意識すべきは「現状の課題」です。例えば、現状の売上が低迷しているという課題があるのであれば、その売上を上げるために必要な行動をとる必要があります。
また、若手社員が少ない会社であれば、若手社員の採用を積極的にしたり、採用担当を増やしたりなどが挙げられます。個人個人が組織にとって何を求められているのか、どういった成果を出せるのかを把握することが大切です。
will-can-mustの情報をまとめる
will-can-mustの要素を洗い出したら、それらの情報をまとめる作業を行います。中でもリクルート社が導入しているwill-can-mustシートを活用すれば、効率よく情報をまとめられるでしょう。
will-can-mustシートでは、will-can-mustそれぞれの項目を書き出します。そして、それらの項目を全て満たす目標を設定していくのです。
とはいえ、Mustの部分は上長と話す必要があるためまずはWillとCanを埋めていきましょう。その中でそれらの項目を満たしながらも組織にとって必要な項目を探していきます。
例えば、営業としてのスキルを生かして社長賞を取りたい社員がいるとします。そこから上長との面談を通して、企業にとってどの分野を強化していくべきなのかなどを具体的に決めていきます。
目標達成に向けて年間・月間でどのように動いていくのかを定められれば目標は設定完了です。このように、まずはWillとCanを洗い出しながら上司や先輩と一緒に目標を決めていきましょう。
面談を通して定期的に振り返る
目標は立てっぱなしではなく定期的に振り返る必要があります。達成に向けて今どれくらいの場所にいるかわからなければモチベーションは維持できません。
また、いつまでも目標達成ができずうやむやなままで終わってしまう可能性もあります。月に1回程度を目安に、will-can-mustシートを活用した面談を設定しましょう。
きちんとwill-can-mustを満たした状態で目標に取り組めているのかを確認しながら、実際にやって見てわかった課題や問題を随時修正していきます。
仮にはじめに設定した目標の達成が難しい場合には、目標を再設定する必要もあります。きちんと期限を定め、それに向かって実現な目標を設定しましょう。
will-can-mustの活用方法
本章では、will-can-mustの活用方法を解説します。
- will-can-mustシートの作成手順
- will-can-mustの分析
- will-can-mustを用いたキャリア
活用方法を知ることで、個人と組織の両方にとって、より効果的な目標設定と成長戦略の立案が可能になります。
will-can-mustシートの作成手順
will-can-mustは、頭の中で考えているだけではあいまいなイメージで終わってしまうことも少なくありません。このフレームワークを有効に活用するためには、シートを作成し、文字に起こしてみることです。
シートの形式にルールはないものの、もっともわかりやすいのはwill、can、mustの3つをグループとして分ける形式です。グループは罫線で仕切ってもいいですし、大きな〇を3つでもいいでしょう。
※イメージ
その中に、自分が考えるwill、can、mustを書き込んでいきます。
ここで大切なのは、それぞれの要素に集中して考えることです。canの欄に記入しているときに「willの欄にも書いたから、これは書かなくていい」などということを考える必要はありません。なぜなら、will、can、mustは重複して当然の要素だからです。
will-can-mustの分析
シートを作成した後は、記入した内容を分析します。各要素がどのように関連しているか、重なっているかを確認します。
例えば、ホテルのフロントで働いている人のケースを考えてみましょう。
- Will:「海外からのお客さまにもレベルの高いサービスを提供したい」
- Can:「英会話が得意」
- Must:「精算時の会計処理を迅速化する」
この場合、willとcanが一致しています。これは、したいこと(高レベルのサービス提供)とできること(英会話)が合致している状況です。つまり、この面では今すぐにでも実行可能であり、現時点での接客レベルは一定以上に達している可能性があります。
一方で、mustは他の二つと異なっています。企業側は多言語対応よりも会計処理の迅速化を求めているようです。
上記のように、will、can、mustの一致・不一致を分析することで、自分の希望、能力、そして組織の要求の関係性を明確に把握できます。
will-can-mustを用いたキャリア
分析結果を基に、自分のキャリアを考えます。理想的には、will、can、mustがすべて一致していることですが、このようなケースは稀です。
上記の例では、willとcanは一致していますが、mustとは異なっています。
この場合、以下のようなキャリア選択が考えられます。
- 現在のポジションでmustに合わせる:会計処理のスキルを向上させ、企業の要求に応える。
- 社内で異動を検討:例えば、ベル係やインフォメーションなど、語学力を活かせるポジションへの移動。
- 転職を検討:外資系ホテルなど、語学力を重視する環境への転職。
重要なのは、will、can、mustが一致していなくても悩まずに、「それならどうすればいいのか」を前向きに考えることです。
以上がwill-can-mustフレームワークの有効な活用法です。
自分の希望(will)と能力(can)を活かしつつ、組織の要求(must)とのバランスを取りながら、最適なキャリアパスを模索しましょう。
will-can-mustの具体例
will-can-mustの内容を理解しても、実践例を知らなければ自社内での活用はできません。そこで本章では、will-can-mustの具体例を2つ提示します。
- 「will」「can」と「must」が一致していないケース
- 人材育成「will」「can」と「must」が一致しているケース
will-can-mustで実現する未来を知ることで、組織全体のパフォーマンス向上を目指せるはずです。
「will」「can」と「must」が一致していないケース
【「will」「can」と「must」が一致していないケース】
| ビジネス | 高級フィットネスジム |
| 出店場所 | 大都市のビジネス街 |
| will(したいこと) | 最新の設備とパーソナルトレーニングで顧客の健康増進に貢献したい |
| can(できること) | 最新のトレーニング機器の導入有資格の専属トレーナーの雇用個別栄養指導プログラムの提供 |
| must(顧客が求めること) | 短時間で効率的に運動し、ストレス解消したい |
上記ケースでは、willとcanの方向性は一致していますが、mustである「顧客が求めること」とは反対方向へ進む方針を打ち出しています。
このまま事業を拡大していくと、顧客のニーズ(短時間での運動)と提供サービス(本格的なトレーニング)のミスマッチが生じ、経営悪化を招くでしょう。
ですのでサービス内容の見直しや、忙しいビジネスパーソン向けの広告に切り替えなど、マーケティング戦略等を変更する必要があります。
「will」「can」と「must」が一致しているケース
【「will」「can」と「must」が一致しているケース】
| ビジネス | 大手IT企業の人材育成部門 |
| 部署 | 社内人材開発センター |
| Will(したいこと) | 従業員の技術スキルとリーダーシップを継続的に向上させ、イノベーションを促進したい |
| Can(できること) | 最新のテクノロジートレーニングプログラムの開発と実施経験豊富な社内講師陣の活用オンラインとオフラインを組み合わせた柔軟な学習環境の提供個別のキャリア開発プランの作成と実施 |
| Must(会社と従業員が求めること) | 急速に変化するIT業界で競争力を維持するための継続的なスキルアップ従業員の長期的なキャリアアップ支援イノベーションを生み出す組織文化の醸成 |
上記ケースでは、3つそれぞれが同じ方向性を向いています。このような状態を目指すと、企業は自社のリソースを最大限に活かしながら、会社や従業員が求めることを解決できるでしょう。
will-can-mustが欠けている人材への3つの対処法
ここでは、will-can-mustそれぞれが欠けている場合にどのようなリスクが起こるか、また欠けている人材への対処方法を紹介します。
- willが欠けている場合
- canが欠けている場合
- mustが欠けている場合
自身や組織の中で Will-Can-Must の欠如している部分を特定し、適切に補えれば、個人のキャリア満足度と組織のパフォーマンス向上につながるでしょう。
1. willが欠けている場合
Will(したいこと)が欠けている場合、会社でMust(すべきこと)が優先され、義務感で働いているケースもあるでしょう。従業員は高いモチベーションを持って働くことができず、不平不満が出てくる可能性もあります。
また、Can(できること)だけ満たされている場合も「仕事はこなせるけど退屈」といった状態になりやすく、退職につながる可能性が高くなります。会社は従業員の希望に耳を傾け、人事配置や業務の割り当てを決定することが大切です。
2. canが欠けている場合
Canが欠けている場合、自分の身の丈に合った仕事につけていない可能性があります。無理している状態では思ったような成果が出せず、本来の自分の能力を発揮できないケースも多いでしょう。
周りからは評価されないため給与も上がらず、大きなストレスを抱えて悩むことも少なくないはずです。会社は従業員の能力やスキルを適正に判断し、各人の能力が活かせる業務へ配置する必要があります。
3. mustが欠けている場合
Mustが欠けている場合、周囲の期待が本人へきちんと伝わっていない可能性があります。正当な役割が与えられないと「何のために働いているのか」と疑問を持ち、モチベーションを失いやすくなります。
周囲の役に立っていると実感させるためにも、従業員に対して役割や期待していることを明確に言語化して伝える姿勢が必要です。
従業員にwill-can-mustを浸透させる方法4選
ここからは、従業員にwill-can-mustを浸透させる4つの方法を紹介します。
- キャリアデザイン研修の実施
- 1on1ミーティングの実施
- 人事評価制度の見直し
- 自発的に人事異動ができる制度の導入
4つの方法を理解し実施することで、組織全体でwill-Can-Mustフレームワークを効果的に活用し、従業員の成長と組織の発展を促進できるでしょう。
1. キャリアデザイン研修の実施
キャリアデザイン研修とは、従業員一人ひとりが持つ強みや役割を把握し、キャリアパスを考えるための研修です。自己診断によって強みを理解する、周囲からの期待や役割を理解することなどに軸を置いた研修では、自分のwill-can-mustを再確認することができます。
各人が進みたいキャリアパスや得意分野を明確にし、自発的に仕事と向き合えるようになるためにも有効な研修です。
2. 1on1ミーティングの実施
上司と部下が定期的に1対1で行う面談「1on1ミーティング」。上司から従業員へ評価を伝える「キャリア面談」とは異なり、よりフランクに悩み相談やアドバイスができるのが魅力です。「失敗した原因はわかる?」「どうすればうまくいったと思う?」など、上司は従業員が自発的に問題を解決できるよう促してあげるのがポイントです。
関連記事:1on1についてまとめた記事はこちら
3. 人事評価制度の見直し
人事評価がぶれていたり、一部の人だけが評価される仕組みになったりしていると、従業員のモチベーションは下がってしまいます。そうならないためにも業務に必要な能力や一人ひとりに期待することなどを再度明確に定義し、評価方法を再設計することも必要です。
各人のmustやwillを目標に取り入れることで、本人の自発的な努力を促すことができます。
関連記事:人事評価制度についてまとめた記事はこちら
4. 自発的に人事異動ができる制度の導入
柔軟な人事異動制度の導入は、従業員のwillを満たすことができます。自分の希望する部署へ移動でき、希望する業務に就ければ、モチベーションもアップするはずです。各部署が異動者を公募する「社内公募制度」や、従業員自らが希望する部署へ自分を売り込む「社内FA制度」などの導入を検討してみるのもよいでしょう。
Will Can Mustに関するよくある質問
本記事では、Will Can Mustについて解説してきました。ここではWill Can Mustについてのよくある質問をまとめています。
Will Can Mustについて理解を深めましょう。
will-can-mustの法則とはなんですか?
will-can-mustの法則とは、キャリア形成や目標達成のために、「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(すべきこと)」の3つの要素を整理し、バランスを取る考え方です。
Willは自身の意欲や興味、Canはスキルや経験、Mustは役割や責任を表します。これらを明確にすることで、主体的なキャリア形成やモチベーション向上に繋げることができます。
will-can-mustの具体例を教えてください
willは興味や関心、canはこれまでに経験したことやスキル、mustは現状の課題
たとえば営業職を想定し、will-can-mustにあてはめると以下のように整理できます。
- will「顧客の課題解決に貢献したい」
- can「コミュニケーション能力が高い」
- must「売上目標を達成する」
次に、エンジニア職にあてはめてみましょう。
- will「最新技術を習得したい」
- can「プログラミングスキルがある」
- must「プロジェクトを納期内に完了させる」
自身の職種や役割に合わせて、3つの要素を具体的に書き出すことで、自己理解が深まります。will-can-mustを理解し、自己表現について役立ててください。
will-can-mustのまとめ
will-can-mustは自分を見つめ、仕事に対するモチベーションを向上させる有効な考え方です。一方で、人事評価制度のトレンドは刻々と変化しており、適切な評価が難しくなっている実情もあります。
「あしたのチーム」では人材育成や企業成長のために必要なチームづくりを支援しています。ぜひシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ビジネス全般に関連したおすすめセミナーのご案内
あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード
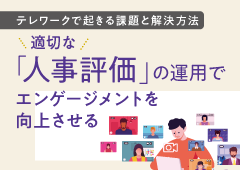
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」
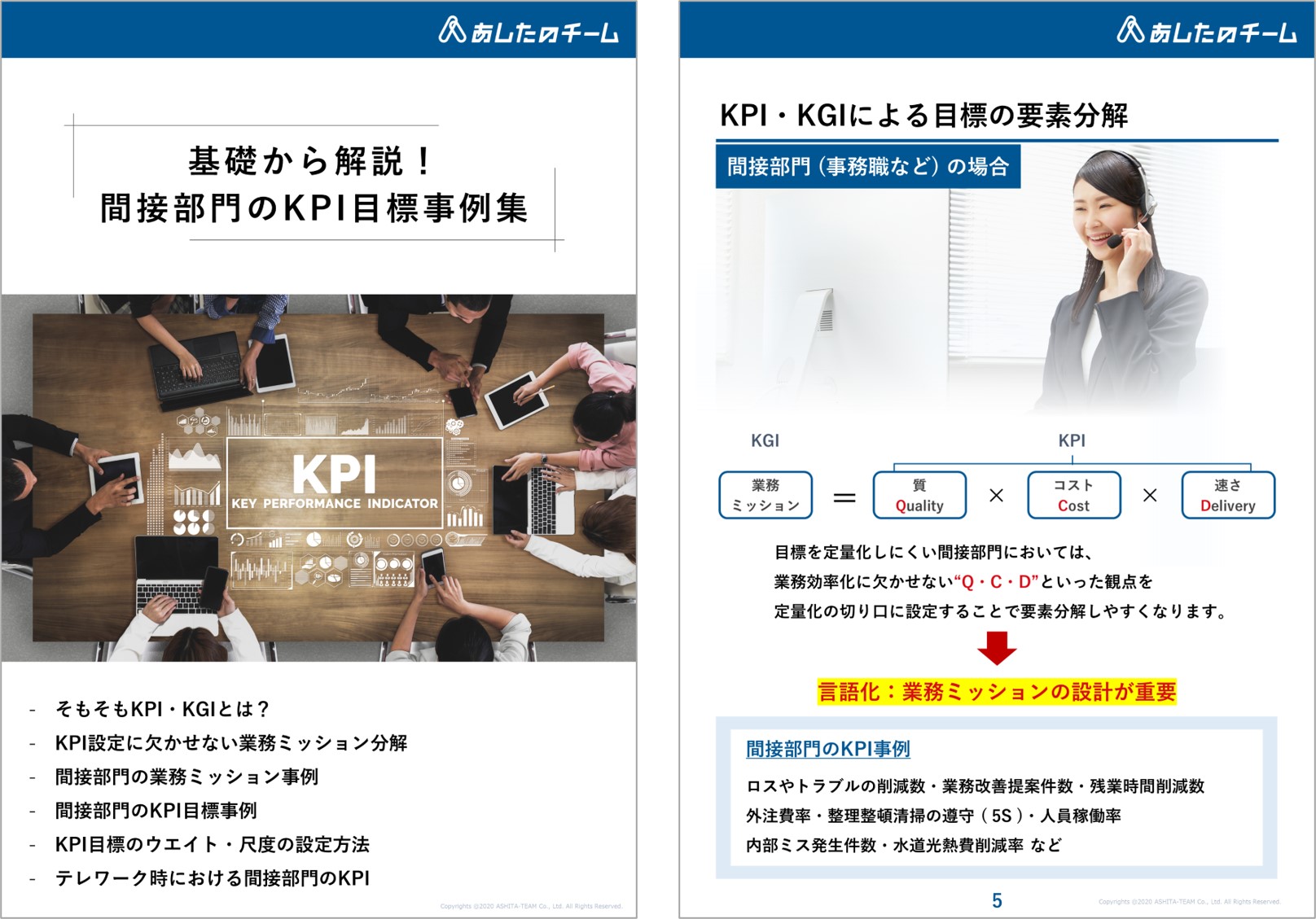
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例
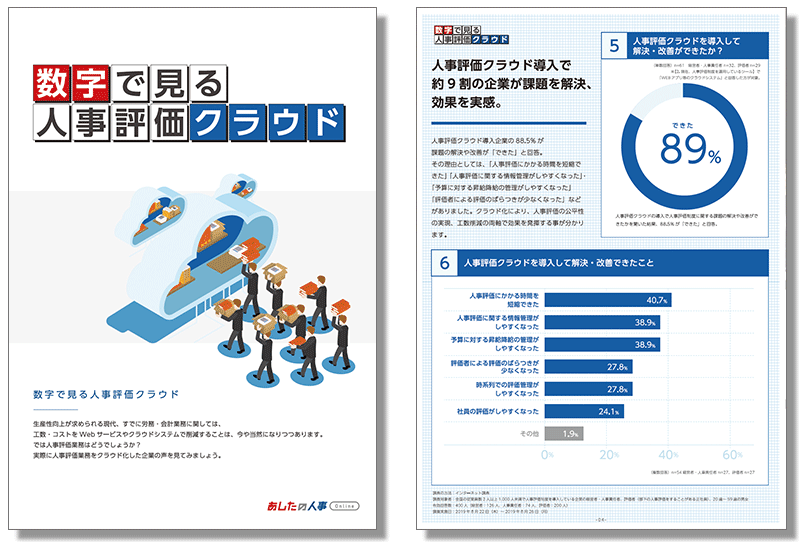
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド
ビジネス全般の課題を解決するサービス紹介
あしたのチームのサービス
導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
あした式人事評価シート
 あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア
あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア