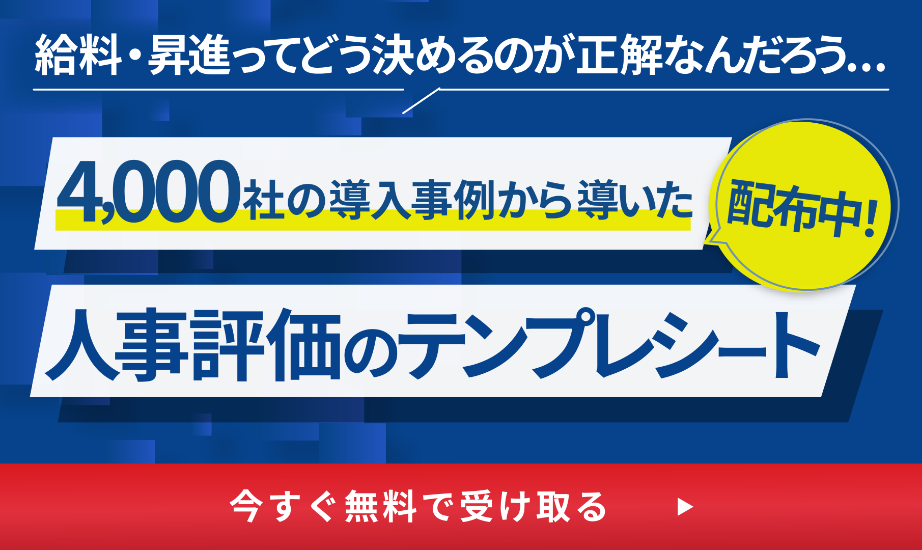コロナ禍において、多くの企業が雇用・人事制度やマネジメント制度の見直しを図っています。従来の「メンバーシップ型雇用」ではなく、「ジョブ型雇用」や「成果主義」に目を向ける企業が増えているようです。
本記事では、ジョブ型雇用と成果主義の違いや、ジョブ型雇用の特徴、注目される背景、企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットについて解説します。併せて、ジョブ型雇用を導入するための準備と流れ、導入に成功した企業事例も紹介しています。自社施策の参考にしてください。
ジョブ型雇用とは?
「ジョブ型雇用」とは、特定の業務に対して人材を確保し、配置する雇用システムのこと。
ジョブ型雇用において、雇用主と従業員は事前に業務内容を明確に定め、雇用契約を結びます。従業員は、契約内の労働だけに責任を負うのが一般的です。
あくまでも特定の業務を単位として雇用契約が結ばれるため、その業務が終了したり、なくなったりした場合は契約が解除されることがほとんどです。
ジョブ型雇用のもとで働く人は、特定の業務にのみ就いて働き続けるため、就業期間が長くなるほど、その業務に熟練することができます。熟練したスキルを身につけ、より良い条件でほかの企業に転職することも可能です。
また、特定の業務に対してのスキルが評価されるため、年齢や男女の差なく雇用されるケースが多いようです。
メンバーシップ型雇用との違い
ジョブ型雇用とよく比較されるのは、先に人材を採用して確保しておき、その人材に対して業務を割り当てていく「メンバーシップ型雇用」です。
「メンバーシップ型雇用」は終身雇用制度、年功序列であるのが特徴です。したがって、業務終了とともに雇用がなくなる場合もあるジョブ型雇用と結び付かない面を持っています。総合職として転勤や異動、ジョブローテーションを行い、長期的な人材育成を目指すため、業務が終了したり組織が統合したりするなどの変化がある場合でも、担当業務を変更しながら雇用は継続されます。
また、ジョブ型雇用は特定の業務に対してのスキルが評価されるため、年齢や男女の差なく雇用されるケースが多いようです。その点において、ジョブ型雇用は、メンバーシップ型雇用と比べ、平等性の高い雇用システムだと言えるでしょう。
成果主義とは?
成果主義とは、その人が仕事において成し遂げた成果や成績、実力によって給与や待遇、役職などが決められる人事制度のこと。
日本の企業では、終身雇用制度、年功序列の考え方によって、勤続年数や年齢に応じて給与や待遇、役職などが割り当てられることが多いのが現状です。成果主義の人事制度が導入されれば、旧来の評価基準や働き方が大きく変わります。
1990年代のバブル崩壊後、業績が悪化した企業は、一定の成果を上げていない従業員に高い給与を支払うことや、勤続年数が長い従業員の人件費が膨れ上がることなど、それまでの年功序列のやり方に課題感を抱くようになります。
それが、多くの企業が成果主義に目を向けるきっかけになりました。
現在では、正社員だけでなく、派遣や請負、パートタイマーなど雇用の選択肢が増え、また、中途採用などの採用制度も当たり前になったことから、一層、勤続年数や年齢だけに目を向けて給与などを決めることが難しくなっています。
そのため、従業員一人一人の成果に応じて評価し、給与などを決定する成果主義を導入する企業が増えています。
関連記事:成果主義の問題点と解決策についてまとめた記事はこちら
ジョブ型雇用と成果主義の違い
業務内容に給与や待遇、役職が紐づいているという点で、ジョブ型雇用と成果主義はよく似ていて、同一の制度と誤解されがちですが、この2つの制度は全く異なるものです。
ジョブ型雇用は、特定の業務があり、それを遂行できる人材を採用します。この場合、採用の時点で人材の評価は行われており、業務を遂行した際の報酬は決まっているのです。
そのため、採用後は担当の業務をきちんと遂行できているかだけがチェックされます。その人の業務のクオリティ、成果の良し悪しにかかわらず、報酬が一律であるという点がジョブ型雇用の特徴です。
また、先に述べたように、ジョブ型雇用は特定の業務を遂行するための採用であるため、その業務が終わったり、なくなったりした場合は人材を雇用しておく必要がなく、該当の従業員は、解雇の対象となりやすいと言えます。
一方、成果主義は、あくまでその人の行った業務のクオリティや成果の良し悪しに応じて給与などを決めていく評価制度ですから、特定の業務のために人材を採用した場合も、人材ありきで採用をして何かしらの業務を割り当てた場合も、どちらにも適応することができます。
そのため、成果主義の制度下では、特定の業務がなくなったからといって、従業員が解雇対象となるケースは少ないと言えるでしょう。
日本でジョブ型雇用が注目されている理由
日本でジョブ型雇用を導入する企業が増えてきました。その背景には何があるのかを解説します。
経団連によるジョブ型雇用の推奨
2022年度の春季労使交渉では、「自社の企業戦略を踏まえたジョブ型雇用の導入・活用」が提言されました。これは2020年の「経営労働政策特別委員会報告」における「日本型雇用システムを見直すべき」という提言と、同じく2021年の「適切な形でジョブ型を組み合わせた『自社型』雇用システムを確立すべき」という提言の延長上にあります。
提言に至った背景には、終身雇用制や一括採用を中心とした日本型雇用システムが、企業の採用と人材育成の方針から見て成立しなくなってきた現状があります。併せて、Society 5.0(サイバー空間とリアル空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会)に対応するには、ジョブ型雇用のほうが向いているという認識があります。
参考:経団連「春季労使交渉・協議の焦点〈4〉」
テレワークの普及による評価制度の見直し
テレワーク導入によって、成果に対する評価の比重が大きくなったのも、日本でジョブ型雇用が注目されている理由です。
テレワークは次のような特徴があります。
- 勤務態度や仕事に対する意欲などを上司が観察しにくい
- 在宅勤務の人、短時間勤務の人など多様な働き方があり、人を基準にした評価をしにくい
このため、個人の職務が明確で、成果物によって生産性を測りやすいジョブ型雇用に移行する企業が増えています。
専門性の高い人材の不足
専門性の高い人材を確保するための手段としても、ジョブ型雇用が注目されています。ジョブ型雇用は現時点でのスキルに見合った給与、待遇を提示して、採用につなげやすいからです。対してメンバーシップ型では、年齢や勤務年数に沿った雇用条件の提示になるため、高いスキルを持った人が魅力を感じないケースが少なくありません。
労働力減少が続く日本では、人材不足は特に深刻です。例えばIT人材は、新規事業創出やDXが進んでいる背景もあって、2030年に40万~80万人不足すると予測されています(※)。このような分野において、ジョブ型雇用はますます注目されていくでしょう。
※出典:経済産業省「参考資料(IT人材育成の状況等について)」
グローバル化やダイバーシティの浸透
ビジネスのグローバル化が進むと、さまざまな国や地域の人がチームを組んで働きます。また、働き方改革でも推奨されているダイバーシティ(人材の多様性)が浸透すれば、育児中の人や障がい者の人など多様な人材が雇用されるため、さまざまな働き方を想定しなければなりません。
しかし、メンバーシップ型は従業員が同じ場所・時間に集まって仕事をすることが想定されているため、グローバル化やダイバーシティに対応するのが困難です。また、ライフ・ワーク・バランスを求めて在宅ワークをする人や、時短勤務を望む人などの多様な働き方も受け入れにくい面があるでしょう。
職務単位で仕事を振り分けられるジョブ型ならば、グローバル化やダイバーシティに柔軟に対応可能です。このため、多様な人材を雇用する企業では、ジョブ型雇用に移行する傾向があります。
企業がジョブ型雇用を導入するメリット
今後、日本でも業務と人材を紐づけたジョブ型雇用が主流になっていくのではないかと言われています。では、ジョブ型雇用にはどのようなメリットがあるでしょうか。
求職者と業務内容のミスマッチが起こりにくい
企業は、遂行すべき業務ありきでそれに適応できる人材を採用するため、求職者のスキルと実際に行う業務内容とのミスマッチが起きづらいと言えるでしょう。採用後、従業員は自身のスキルを最大限に活かして業務に取り組み、一定の成果が期待できます。
また、契約時にしっかりと業務内容が示されるので、従業員は希望しない業務を命じられることがありません。また、特定の業務に従事し続けることで、スキルを磨き、専門性を高めることができます。
リモートワーク・テレワークとの相性が良い
与えられた業務をしっかり遂行できてさえいれば、企業は労働時間や休暇の取得についての裁量を従業員側に持たせることが多く、リモートワークやテレワークとの相性が良いと言えるでしょう。
従業員は、契約の範囲内で業務にあたるため、関係のない仕事を任されて長時間労働を課されることがないので残業が少なく、転勤や異動の義務もありません。従業員の通勤の負担が軽減されることも期待できます。
勤務体系次第では、雇用主側のマネジメント面の負担も軽減するでしょう。
スキルや能力のある若手が活躍できる
給与や待遇が、任せられる業務の難易度や成果に応じて決まるので、スキルや経験があり、成果を残せる人ほど高収入を得ることができます。そのため、業務を遂行できる能力さえあれば、若くても重要な仕事に就くことが可能です。
また、リモートワークやテレワークによる勤務が可能になれば、能力がありながらも子育てや介護など、労働時間や勤務場所といった障壁によって活躍できずにいる人材が、力を発揮する場を得ることもできるでしょう。
無駄がなくなり、業務の効率化につながる
それぞれの従業員に任される業務内容や責任の範囲が明確になり、業務における無駄がなくなって、業務の効率化につながります。
また、特定の業務に対して専門のスキルや能力を持つ人材を獲得できれば、クオリティの高いアウトプットが期待でき、企業全体の生産性も向上するでしょう。
年齢や勤務年数に応じて給与が増えていく年功序列制度と違い、成果に基づいて給与が支払われるため、長い目で見ると人件費の削減も可能になります。
無駄がなくなり、人件費を削減しやすい
ジョブ型雇用の導入によって業務内容や責任の範囲が明確になり、業務の無駄がなくなれば、人件費も削減できます。特に専門職やプロフェッショナル型のエンジニアなどでは、プロジェクト単位で雇用するケースも珍しくありません。必要な人材を、必要なときに、必要な人数だけ雇用すれば、人件費を抑制できます。
正当な人事評価を実現しやすい
ジョブ型は成果が明確なため、客観的な評価がしやすくなるのが特徴です。売上への貢献度や成果物のクオリティ、所有資格など、数値化しやすい要素で判断されます。このため、上司との人間関係が影響したり、性別や年齢で評価が下がったりといった不公平が生じにくいのが特徴です。
企業がジョブ型雇用を導入するデメリット
一方で、ジョブ型雇用にはいくつかのデメリットも存在します。どのような点がデメリットと言えるのか、解説します。
スキルアップはできるがキャリアアップが難しい
従業員は、専門性を持って同一業務に就き続けるため、特定の分野のスキルや能力を磨くことが可能です。
しかしその一方で、その分野でしか能力を発揮できないため、ポストが空かなければ役職に就くことが難しいと言えます。キャリアアップを目指して転職を考える際も、専門分野が狭い世界であればあるほど、募集の数が少なく、チャンスに出合いにくいと考えられます。
また、任された業務が終われば、解雇される可能性も大いにあります。
高い専門性を持つ人材の採用が難しい
遂行してほしい業務内容を明確にして求職者を募るため、それに見合うスキルや能力のある人材を見つけるのが難しいという点もデメリットの一つです。
また、契約上、社内で他の業務にあたってもらうことができないため、ある部署で急な欠員が出たときなどに、ジョブ型雇用で採用した人材を代替要員としてあてがうことはできません。
雇用主側は、人材が必要になったタイミングで適任の求職者がいるとは限らないことを留意しておく必要があります。
組織への帰属感やチームワークを育みにくい
ジョブ型雇用の場合、従業員は組織ではなく与えられた業務にコミットしているため、組織への帰属感や忠誠心は低くなると言えるでしょう。また、高い専門性を持つ人材は、より良い条件を求めて転職をすることが考えられます。
そのため、人材が定着しにくくなり、チームワークが弱くなる懸念もあります。チームで行う作業や長期的なプロジェクトが多い職場には、ジョブ型雇用マッチしない可能性がありますので、導入についてはじっくり検討しましょう。
スキルや能力不足は自己責任となる
企業は、特定の業務を遂行できる能力を持った人を採用します。そのため、社内ではほとんどトレーニングや教育を行いません。従業員は、自分の持つスキルや能力だけを武器にして業務にあたらなくてはなりません。
もし、スキルアップを目指すのであれば、社外で学ぶなど、自主的な努力が必要です。また、与えられた業務において期待されている成果を残せない場合は、能力不足と見なされ、解雇される可能性もあります。
異動や配置転換がしづらくなる
ジョブ型雇用は、会社側の都合による異動や配置転換がしにくい面があります。例えば、プログラマーとして雇用した人材に事務職に異動してもらうには、本人とよく話し合って了承を得る必要があるでしょう。
また、異動や配置転換を繰り返しながら、幅広い業務を経験させて育成するゼネラリストに対しても、ジョブ型雇用は不向きです。そのため、スペシャリストのみにジョブ型雇用を適用して、ゼネラリストには適用しない企業もあります。
評価制度や給与体系を見直す必要がある
ジョブ型雇用を新規導入すると、評価制度や給与体系を見直す必要が出てきます。ジョブ型雇用はおおまかに言えば、リーダーや定型業務従事者など、すべてのポジションに価値を付け、それに値する人材を当てはめる形式になります。したがって、年功序列と職能等級を基準に設計された評価制度や給与体系と相容れない部分があるのです。
ジョブ型雇用を導入すると、以前から勤務している従業員の役職や給与が下がるケースも珍しくありません。このため導入前には丁寧な説明が必要です。
従業員にとってのジョブ型雇用のメリット
従業員にとって、ジョブ型雇用はどのようなメリットがあるのでしょうか。従業員の立場からもジョブ型雇用を捉えておくことで、より自社に合った制度を整えやすくなるでしょう。
自分の得意分野に集中できる
ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプション(職務内容を詳しく記述した文書)にある業務以外を依頼されにくいのが特徴です。仮にプログラマーとして雇用されたのであれば、営業活動や無関係な事務仕事などを任されることはありません。つまり、自分の得意分野に集中しやすいのがメリットです。
また、入社後の業務ミスマッチのリスクも減らせます。ジョブ型雇用の場合は、一般的に採用された時点で配属先の部署と職種が決まっています。そのため、メンバーシップ型のように入社後に配属先が決まって、本人の希望が叶えられないといった事態が起こりません。
専門的なスキルを高めやすい
ジョブ型雇用では特定の業務に長期間従事するため、専門的なスキルを高めやすいのもメリットです。スキル獲得の範囲は限られるものの、知識や技能を深く追求していけます。この点、数年おきに業務が変わるようなゼネラリストと対照的です。
専門スキルを磨きやすいメリットは、エンジニアや士業などの専門職でない人でも変わりません。人事や営業、経理などの分野で一般職と呼ばれるような業務にも、やはりそれぞれの専門性があります。ジョブ型雇用で長期間同じ業務に携わることで、特定のスキルを高めていけるでしょう。
成果を出せば給与に反映される
繰り返しになりますが、職務内容や求められるスキルが明確なジョブ型雇用では、自分の得意分野に集中して成果を出しやすいのが特徴です。そして成果を出せれば、それに応じて給与や待遇が上がります。
この点、成果を出しても出さなくても給与が一律的な年功序列型と対照的です。自分の実力で給与アップを目指したい人にとっては、モチベーションを維持しやすい環境といえるでしょう。
日本企業では、特に専門職のモチベーションアップ効果が高いとされています。というのも、メンバーシップ型雇用が多い日本では、専門職よりマネジメント層のほうが偉いとされ、給与が高い傾向にあるからです。ジョブ型雇用であれば、専門職として正当な給与を受けやすいのがメリットです。
従業員にとってのジョブ型雇用のデメリット
ジョブ型雇用には多くのメリットがありますが、業務が不要になれば解雇されたり、成果を出さなければ評価が下がったりするシビアな面もあります。ジョブ型雇用のデメリットを、従業員の立場からみてみましょう。
業務が無くなると失職する可能性が高い
ジョブ型雇用では、業務や職種が不要になった際に、失職する恐れが高くなります。実際、IT企業においては、システム開発のプロジェクト単位でエンジニア職を雇用するケースも珍しくありません。すでに高いスキルを持っている人なら、すぐに次の仕事が見つかるでしょうが、成長途中の人の場合、経済的に不安定になるリスクがあるのです。
ただ日本企業の場合、ジョブ型雇用といっても仕事がなくなると同時に雇用自体がなくなる欧米型のジョブ型雇用を採用している企業はあまり多くありません。日本では人材確保が難しい事情もあるため、リスキリング(ビジネス環境の変化によって新たに必要とされる知識やスキルを習得させる人材戦略)を実施して、違う業務に就いてもらう企業も多くあります。
成果が出なければ評価されない
ジョブ型雇用は単に特定の業務に従事すればよいわけではなく、成果主義とセットで運用されるのが一般的です。成果が出なければ、当然、人事評価は下がります。また、雇用条件にもよりますが、解雇されるリスクもあります。
職務によっては、評価に対する不公平感を持つ場合もあるでしょう。例えば、コールセンター業務で親身な対応をしているのに、対応時間が長いとして評価が下がってしまうケースがあります。また、研究職では、すぐに成果が出る研究内容ばかりとは限らないでしょう。
このため、短期的な成果、利益にこだわらず、腰を据えて仕事に取り組みたい人にとっては、ジョブ型雇用の成果主義がプレッシャーになる可能性があります。
自身で専門性を高め続けなければならない
ジョブ型雇用では、メンバーシップ型雇用と異なり、手厚い研修や教育が少ない傾向があります。メンバーシップ型雇用の場合、新卒採用が中心のため、スキルアップのための社内研修やキャリアアップのための外部研修などを積極的に行います。
一方、ジョブ型雇用は中途採用で即戦力を期待するケースが多いため、研修や教育の施策が乏しくなりがちです。
したがって、従業員は自ら専門性を高め続けなければなりません。成長意識が低ければ、より高度な業務にステップアップできないかもしれません。また、新たな知識や技能が必要になった際に、不要な人材となってしまう可能性もあります。
ただし、このジョブ型雇用の弱点を補うために、一部の企業は教育研修や社外講座のメニューを複数提供して、従業員自ら選んで利用してもらう制度を取り入れています。このような企業であれば、主体性を持ちながら、専門性を高めやすいといえるでしょう。
ジョブ型雇用を導入するには?
ここからはジョブ型雇用を導入する企業が、どのような手順で準備を進めるのか解説します。
職務内容・要件を定義する
はじめに職務内容を決めます。具体的には以下のような内容です。
- 職務名称
- 職務目的
- 職種等級
- 業務内容
- 職務および責任の範囲
続いて、ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成して、職務内容を詳しく定義します。ジョブディスクリプションには先ほどの職務内容に加えて、次のような職務要件を記述します。
- 求められるスキルや技能、資格:普通自動車免許、TOEIC○○点以上、営業経験3年以上、など
- 業務内容の詳細:新規顧客への営業、発注書の手配、など
- 職務および責任の範囲の詳細:自社商材の営業活動、自社商材の販路拡大に貢献する、など
- ヒューマンスキル:顧客の成功体験を高めようとする姿勢、知らない分野を積極的に探究する好奇心、など
給与やインセンティブを設定する
次に職務に応じて給与やインセンティブを設定します。ここでの重要なポイントは、職種や役職、責任範囲、予想される成果に見合った報酬水準を設定することです。
ジョブ型雇用では、メンバーシップ型雇用のように年齢や勤務年数、将来期待する貢献などは重視しません。あくまで職務を基準に報酬水準を決めていきましょう。
ジョブ型雇用の給与やインセンティブは、市場価値と比べたときの妥当性が重要です。市場価値より低すぎてしまえば、従業員はより高い給与を求めて離職しやすくなります。
ジョブ型雇用に適した評価制度を整備する
メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に移行した場合は、評価制度の更新も必要です。具体的には、勤続年数が高いほど賃金水準が高くなる年功序列方式の評価制度などを見直す必要が出てきます。
ジョブ型雇用では、明確な成果を持って評価するのが特徴です。したがって、上司や人事担当者の主観的な判断が入りにくい、納得感の高い評価基準を設計していきましょう。
とはいえ、現実的には「職種別の給与を設定するのが難しい」「そもそも職務を定義できないポジションがある」など、ジョブ型雇用導入後の評価制度に課題を抱える企業は少なくありません。従業員の納得感が高い評価制度の構築なら「あしたのチーム」にぜひご相談ください。
関連記事:ジョブ型雇用に適した人材評価制度についてまとめた記事はこちら
まずは管理職から導入してみる
ジョブ型雇用は、組織運営や従業員の業務などに大きな影響を与える可能性があります。このため、まずは役割や責任範囲が明確な管理職に限定して取り組むのも一つの方法です。
実際、ジョブ型雇用を全面的に取り入れた日本企業の多くも「管理職→一般職」という流れで、適用を進めています。管理職が身を持ってジョブ型雇用を理解していれば、部下のマネジメントや人事評価の際にも適切に対応できる効果も期待できるでしょう。
ただ、日本企業の管理職には、バブル崩壊とその後の人出不足によってプレイングマネージャーが多いのが実情です。ジョブ型雇用はプレイングマネージャーのような横断的な業務に向かないため、管理職の働き方の見直しから検討しなければならない場合もあります。
ジョブ型雇用の導入に成功した5つの企業例
日本においては、大企業を中心にジョブ型雇用に率先して取り組んでいます。ジョブ型雇用の導入に成功した企業事例を5つ紹介します。
KDDI
KDDIは外的要因として、「デジタル化の加速」「人生100年時代」に対応することへの課題を抱えていました。また社内の課題としては事業領域拡大、若手人材の確保と育成、人財活用のスピードアップなどがありました。
これらの課題解決の解決する方法として設計されたのが「KDDI版ジョブ型人事制度」です。KDDI版ジョブ型人事制度は、欧米型ジョブ型雇用であまり重視されない人間力の評価や、多様な成長機会の提供などを加えているのが特徴です。従来のKDDIらしさを大切にしながら職務領域を明確にできた、とKDDIは述べています。
ソニー
創業当初からソニーが大切にしてきたのは、社員と会社が対等に向き合い、答え合うカルチャーです。このカルチャーを守るために、ソニーは2015年に役割に応じて等級を定義した「ジョブグレード(JG)制度」の導入を決定します。
JG制度の大きな特徴は、その時々の役割によって、等級・処遇をシームレスに変えられる点です。例えば、マネジメント等級群から、上級担当者として現場に戻るような異動も一般的な企業より容易です。企業内での適材適所が活性化され、企業としての生産性が高まります。
日立製作所
グローバル企業に成長した日立製作所は、従業員数約30万人のうち、過半数が外国籍です。したがって、グローバルスタンダードのジョブ型雇用を取り入れるのは、必然的な流れだったといいます。
また、日本においても、ワーク・ライフ・バランスを大切にする社員が増えたなか、職務を明確に限定したジョブ型のほうが、働きやすい環境を提供できるメリットがありました。
2020年4月からは「ジョブ型」雇用・採用をより強化し、技術系職種では配属先と職種を確約する採用活動を展開しています。この仕組みは入社後のミスマッチを減らすだけでなく、近年の傾向である「就社<就職」という応募者のニーズに合っているということです。
資生堂
「強い個が強い会社をつくる」を信念とする資生堂は、2021年から、ジョブ型人事制度を管理職と総合職(美容職・生産技術職を除く)に適応しています。
人事評価の基準を個人の能力から職務(ジョブ)に移行することで、グローバルスタンダードに沿った評価と処遇の制度を整えました。各部署における専門スキルや職務内容を明確できたために、各社員がキャリアアップを自覚的に考える効果が生まれているということです。
富士通
富士通はダイバーシティ推進をイノベーション創出の基盤と考え、「ジョブ型人材マネジメント」の考え方に基づく新たな人事制度を導入しました。適用規模は大きく、国内グループの一般社員約4万5,000人が対象です。
制度運用にあたっては、従業員一人ずつにジョブディスクリプションを作成しました。また、職責の高さを定めた「FUJITSU Level」と、レベルに応じた報酬水準を作成。幹部社員にはグローバル共通の評価制度「Connect」を定めました。
併せてリスキリング・アップスキリング教育の充実、1on1ミーティングの実施などのサポートを手厚くして、ジョブ型雇用のデメリットを抑える工夫もしています。
自社に適した雇用システムを構築しよう
ジョブ型雇用を導入する・しないにかかわらず、雇用システムを見直す場合は、これまでのシステム、そして導入を検討しているシステムの特徴やメリット・デメリットを企業側・従業員双方の立場からよく理解することが必要です。ジョブ型雇用導入にともなう職務内容や給与制度、評価制度の見直しも含めて、準備を進めていきましょう。
具体的なイメージがわかない場合には、先行事例が参考になります。日本では大手企業を中心にジョブ型雇用導入が進んでおり、従来のメンバーシップ制の良さを残しながら上手に取り入れている事例も少なくありません。
また、現在では中小企業にもジョブ型雇用導入の関心が高まっており、事例も増え続けています。 ジョブ型雇用の人事評価制度の設計をサポートしている業者や、人事評価システムを提供している業者もありますので、必要に応じて活用するとよいでしょう。
あしたのチームのサービスは、従業員の納得感が高い評価制度の構築をサポート致します。導入企業4000社の実績と創業以来10年以上の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。ぜひ一度、ご相談ください。

人事評価に関連したおすすめセミナーのご案内
人事評価の課題を解決するサービス紹介
あしたのチームのサービス
導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
サービスガイド
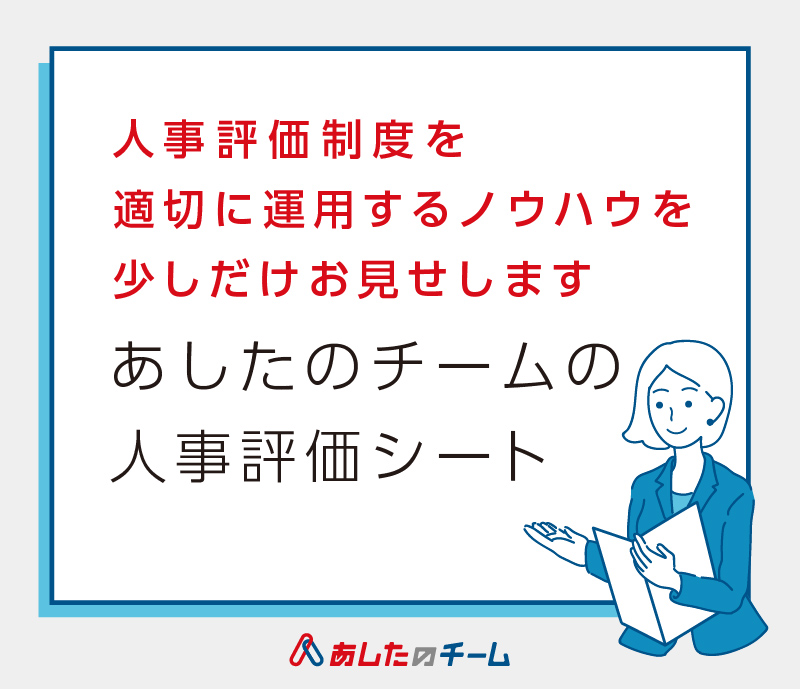
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
あした式人事評価シート
 あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア
あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア