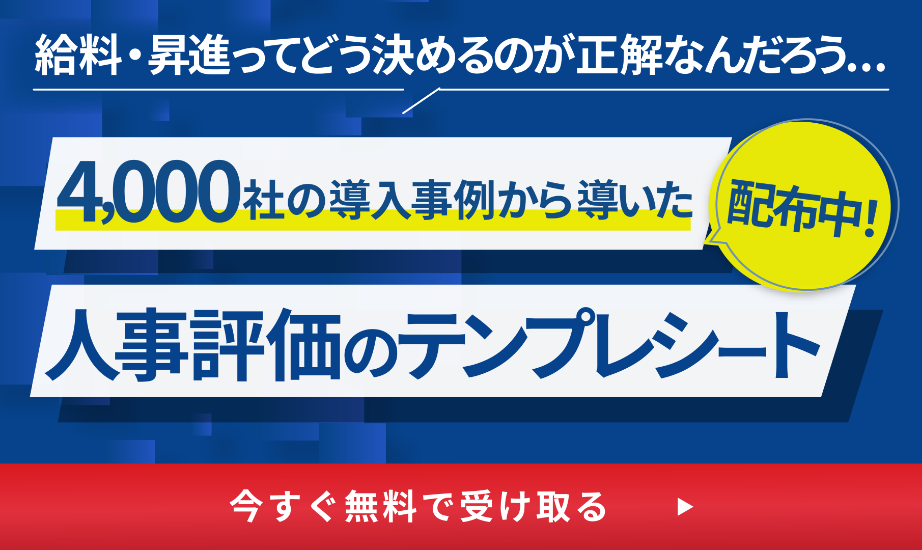ボーナスとは、毎月の給与とは別に支給される特別報酬のことです。企業の従業員や業績の幅によって支給額は大きく異なります。
株式会社フリーウェイジャパンによると、2024年冬における中小企業のボーナスは51.2万円ほどと言われています。
しかし、ボーナスの仕組みや大企業や他の中小企業との違いが気になる方も少なくありません。
本記事では、中小企業のボーナスについて支給される側もする側も知っておくべき知識を紹介します。
目次
2025年最新!中小企業のボーナス平均額
無料の会計ソフトを提供する「株式会社フリーウェイジャパン」の調査によると、中小企業における2024年冬のボーナス平均額は約51.2万円でした。
ボーナスが支給された従業員に支給額をアンケートを実施したところ、「10万円~20万円未満」が最多の23.1%、次に「30万~40万円未満」が15.4%という結果でした。
2023年の冬と比較すると、支給額に「変化なし」と答えた人が46.2%ではあるものの、「やや増加した」と回答した人が42.3%いたことから、少なからず支給額は上昇傾向にあったと言えるでしょう。
中小企業のボーナスの平均額とは
ここで、中小企業のボーナスの平均額はどの程度なのか、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」をもとに、一般的な水準を紹介します。
まず、事業所規模5~29人の企業は、2023年の年末実績で全業種平均が27万5,390円でした。業種別にみると、電気・ガス・熱供給等のインフラ系企業は約58万円と最も高く、金融業・保険業は約54万円と続き、平均の2倍ほどになっています。
一方、医療・福祉(約20万円)や生活関連サービス業等(約12万円)、そして飲食サービス業等(約4.6万円)が平均を下回っているという結果でした。
次に、従業員規模30~99人の企業について、同じく2022年年末実績を見ると、全業種平均が35万572円とやや高めです。業種別のうち最も高かったのは電気・ガス・熱供給等で約77万円となっており、金融業・保険業が約61万円と続きます。
一方、医療・福祉(約19万円)や飲食サービスなど業等(約6.7万円)が平均を大きく下回っており、その他サービス業等(約30万円)もわずかに平均を下回っています。これらの傾向は、事業所規模5~29人の傾向と同様の結果でした。
大企業と中小企業のボーナス平均額の差は?
先述の通り、2024年夏実績での中小企業のボーナス平均額は約35万円でした。
一方、一般財団法人 労務行政研究所が東証プライム上場企業を対象に行った調査によると、2024年夏ののボーナス妥結額は平均で84万6021円という結果に。
以上のことから、大企業と中小企業のボーナス平均額は約50万円ほど違うことがわかります。
中小企業のボーナスは何ヶ月分?
従業員へのボーナス額を決めるにあたって、他の中小企業がどのくらい支払っているのか気になる方が多いのではないでしょうか。
昭和58年に設立し、中小企業を中心に会計業務を担っている税理士法人 吉田士会計の調査によると、中小企業の賞与額は「月給0.8~0.9か月分」という結果でした。
上記の賞与平均額は、従業員数およそ35名前後の中小企業の賞与支給額を平均にしたものなので、ボーナスを支払っていない中小企業を加えるとさらに支給額は少なくなると言えます。
ボーナス支給なしの中小企業の割合
厚生労働省のデータによると、2023年に夏のボーナスが支払われた中小企業は、全業種の約66%でした。(参考記事:毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要)
2023年冬のボーナスでも、中小企業では約70%の支給率でしたので、約3割の中小企業ではボーナスが支給されていないことがわかります。
上記のデータから、ボーナスが支給されており、金額が月給の約1か月分であれば、「他の中小企業と比べて待遇は悪くない」と言えるでしょう。
ボーナスの内訳を理解できる
平均支給額・計算方法を大公開
無料PDFダウンロードはこちらから>>
そもそもボーナスとは?
そもそも、ボーナスとはどのような定義なのでしょうか。ここでは、ボーナスの定義や種類、近年増加している業績連動型賞与を紹介します。
ボーナスは、企業業績の配分
厚生労働省はボーナス(賞与)を
「定期又は臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」
と定義しています。そのため、毎月の給与とは違い、その都度支給額を決定する必要があります。
ボーナスの種類
従来は単純に基本給に対して一律〇ヵ月を乗じて支給額を決める「給与連動型」が一般的でした。
しかし、現在では企業の業績に応じて賞与総額(賞与原資)を決定する「業績連動型」が主流となりつつあります。
賞与総額(賞与原資)が決まったら、人事評価などをもとに配分を行い、最終的に個別賞与額を決定します。
増える業績連動型賞与
従来の「給与連動型」は基本給比例方式で計算できるため、予算どおりの場合は非常に計算しやすいでしょう。
しかし、企業のために必死に努力してくれた社員には適切な評価が求められます。
努力を評価すると同時にエンゲージメントを高める効果もあるとして「業績連動型」を選択する企業が増えています。
中小企業のボーナスがもらえるタイミングはいつ?
一般的な支給のタイミングは夏と冬の年2回です。
- 夏季賞与:6月下旬から7月上旬頃
- 冬季賞与:12月中
上記が一般的です。明確な支給日を知りたい方は、就業規則や雇用契約書をみるのが確実です。
ボーナス・賞与総額(賞与原資)の算出方法
賞与総額(賞与原資)を決定するベースとなる業績指標は、
経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)
営業利益(売上総利益-販売管理費および一般管理費)
上記のどちらかである企業が多いといえます。
そもそも「賞与とは利益配分」という考え方があるためでしょう。
賞与総額の算出方法には大きく2つの方法があります。
1つは、業績指標にもとづいて算出した利益比率とそれに連動した平均支給月数を決めておく方法です。たとえば、半期売上高対経常利益比率が〇%だった場合は、半期賞与支給月数は平均〇ヵ月となります。
もう1つは、業績指標にあらかじめ決めておいた一定の係数を乗じることによって賞与総額を算出する方法です。シンプルな方法ではあるものの、運用面では柔軟に使えない部分もあり、前者の方法を使う企業が多い傾向にあります。
中小企業の個別賞与額の算出方法
社員への個別の賞与額を算出するにはさまざまな方法があり、中小企業ではボーナスを算出する際に迷うことがあります。ここでは、主なボーナス算出方法を紹介します。
算出方法の主な例
個別賞与額の算出には、多くの場合、人事評価を活用します。
一般的によく使われているのは、「基準額×平均支給月数×評価係数」の計算方法です。
基準額とは基本給+各種手当(何が含まれるかはその企業の就業規則などで規定)のことであり、それにすでに算出された平均支給月数を乗じ、さらに人事評価の結果にもとづいた評価係数を乗じます。
評価係数の基準は、企業によってそれぞれ設定している場合が多いでしょう。たとえば、人事評価がSの場合の評価係数は1.2といった形です。
また、評価ポイントを使った賞与配分方法もあります。人事評価結果に、役職や資格・スキルなどを等級(ランク)に分け、それぞれの係数を乗じて算出した評価ポイントによって賞与を配分する方法です。
計算方法の一例としては、
各人の評価ポイント(評価点×等級別係数)×1ポイントあたり単価(賞与原資÷全社員の評価ポイント合計)
などとなります。役職や資格・スキルなどを加味した等級別係数を乗じることにより、企業への貢献度の高い人の賞与額が高くなります。
ボーナスから引かれる税金と保険料は?
ボーナスは従業員の頑張りを評価し、その対価として支払われる特別な給与ですが、受け取る際には税金や保険料が引かれることを理解しておく必要があります。
ボーナスから引かれる税金と保険料は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
所得税
ボーナスは給与と同様に、所得税の課税対象です。
ボーナス支給月の前月の給与(社会保険料控除後)を基準に、国税庁が発表した「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して税率を決定します。
| 源泉徴収額 = 賞与から社会保険料等を差し引いた金額 × 源泉徴収税額の算出率 |
また、源泉徴収された所得税額は、年末調整で「年間の所得税額と源泉徴収された所得税額の差額」が還付または追徴される場合があります。
ボーナスの金額が大きいほど税率は高くなり、扶養家族が多いほど所得税額は軽減されます。
健康保険料
健康保険は、病気や怪我をした際に医療費の負担を軽減するための制度です。ボーナスからも健康保険料が引かれ、保険料率は加入している健康保険組合によって異なります。
健康保険料率は都道府県別に定められています。健康保険料の計算式は以下のとおりです。
| 賞与・ボーナスから控除される健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率×1/2 |
また、40歳から64歳までは介護保険料が加わるため、引かれる保険料が増えます。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、国民年金に上乗せして、年金を受け取れる公的年金制度です。ボーナスからも厚生年金保険料が引かれます。
厚生年金の保険料の計算式は以下のとおりです。
| 賞与・ボーナスから控除される厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率(183/1000)× 1/2 |
雇用保険料
雇用保険は、育児休業給付や失業した際の手当、求職者支援などを支える公的保険制度です。ボーナスの総支給額に雇用保険料率をかけて算出します。
| 賞与・ボーナスから控除される雇用保険料 = 賞与支給額 × 雇用保険料率(労働者負担) |
雇用保険料率は、事業の種類や、労働者と雇用主によっても異なります。
中小企業がボーナスを支給する3つのメリット
中小企業がボーナスを支給するメリットは、以下の3つです。
メリットをうまく活用することで、企業全体の成長と安定につながるでしょう。それぞれ、詳しく解説します。
1. 従業員のモチベーションが向上する
中小企業に賞与制度を導入すると、従業員のモチベーションアップに寄与します。
金銭的な報酬は、従業員の努力を認め、評価する具体的な形となります。これにより、従業員は自身の貢献が会社に認められていると実感し、さらなる努力への動機づけとなります。
モチベーションが上がることで生産性が向上するため、結果的に企業全体の成長にもつながるでしょう。
2. 利益を従業員へ還元できる
賞与であるボーナスは、本来会社の業績にもとづき支払うもので「利益還元金」です。
業績が好調の際は、従業員へ還元したいと考える企業も多いでしょう。しかし、明確なルールがないと還元方法に迷うことがあります。
決算賞与や業績連動型賞与を採用し、利益還元を仕組み化すれば、利益を確実に従業員へ還元できます。
3. 従業員エンゲージメントを高められる
従業員エンゲージメントが高まると、離職率の低下や業績アップにつながる傾向があります。
従業員が会社のビジョンに共感し自発的に貢献したいと思える状態にするためには、企業理念やビジョンを従業員へ浸透させることが必要です。その上で、従業員の働きやすい環境を整備していきます。
賞与の導入は、働きやすい環境を作る一環として活用できるでしょう。公正な賞与制度を導入できれば、従業員エンゲージメントを高めることが期待可能です。これにより、企業と従業員の関係がより強固になり、長期的な成功につながるでしょう。
賃金体系を見直す際に意識すべき3つのポイント
ここまで、中小企業におけるボーナスの算出方法を解説してきました。次に本章では、賃金体系を見直す際に意識すべき3つのポイントを解説します。
中小企業の経営者は、タイミングや制度設計など、さまざまなことに気を配りながら賃金体系を見直していきましょう。
1. ボーナス額の算定理由を明確に説明する
中小企業やベンチャー企業に限らず、業績に応じてボーナス支給の見送りや支給額が少なくなってしまう場合もあるでしょう。しかしながら企業の発展のために貢献してくれた社員への説明を怠ると、その後の信頼関係に良い影響はありません。
ボーナス支給の有無や総額の理由など、企業としての分析結果や今後の経営戦略などを社員にしっかりと説明する責任が企業にはあります。
社員に対しての誠実な説明は、信頼関係の構築につながります。これにより、社員一丸となって目標に向かって頑張っていくためのエンゲージメントが向上し、企業の長期的な成功にも寄与するでしょう。
2. 運用しやすい制度設計にする
制度設計をなるべくシンプルかつ明確にすると、運用がスムーズになります。
もし計算方法が複雑であったり、算定基準が曖昧であったりすると、企業側の運用が困難になるばかりか、社員にとってもわかりにくい制度になってしまいます。
ボーナスの算定方法や評価基準を設計する際は、実際の適用を考慮に入れて、わかりやすい体系を目指しましょう。
3. 適切なタイミングで新制度に移行する
新制度を導入する際は、適切なタイミングを見極めることも重要です。
大きなプロジェクトの途中など中途半端なタイミングで新制度に移行してしまうと、社員に余分な労力をかけてしまい、混乱を招くリスクもあります。
組織改編や業務の区切りがつく時期など、制度導入のタイミングを選ぶことでスムーズな移行が可能です。
適切なボーナス額を算出
支給ルールから計算方法まで一気に解決
ボーナスの損金算入
ボーナスの損金算入方法を解説します。
ここでいう損金算入とは、企業の利益を計算する際に、経費として認められ、課税対象の利益から控除できることを意味します。
上記ポイントを理解すれば、企業の経理業務や税務申告でボーナスを適切に処理するための知識が得られます。
従業員のボーナスは損金算入できる
ボーナスは原則、従業員に支払った事業年度の損金になります。
ただし、「すべての従業員に対し支給の通知を行い、かつ決算日以後1ヵ月以内に支払っていなければいけない」という条件があります。(出典:法人税法施行令 第72条の3)
なお、役員のボーナスは損金として算入できません。
損金算入できる時期は支給した日の事業年度
従業員に対して支給した賞与の損金参入時期は、実際にその支払いが行われた日に属する事業年度が原則です。
国税庁では、「使用人賞与の損金参入時期」に関する税の質問回答で下記のように述べられています。
「労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)」
役員へのボーナスは損金算入できない
役員報酬は原則として損金算入できません。意図的に課税所得や税金を調整できるため、租税回避行為につながる恐れがあるからです。
そのため、役員に支払ったボーナスは税金が課されます。
ボーナスを損金算入(決算賞与)するための要件
具体的な要件は、以下のとおりです。
- 「対象者に対して支給額が個別に通知されている」
- 「決算日の翌日から1ヵ月以内に支給する」
- 「通知どおりの金額が支給されている」
(根拠法令:法人税法施行令第72条の3)
上記3つが条件となります。
ボーナスは支給しなくても良い
ボーナスは必ず支給しなければならないものではないため、支給をしないという選択肢もあります。
ボーナスを支給しなければ、人件費の管理がしやすくなります。ボーナス支給後の時期にまとまって退職者が出ることも防げるでしょう。
一方、ボーナスがないと給与面から従業員のモチベーションをアップさせられません。もともと支給していたボーナスを廃止する場合はなおさらです。その結果、生産性が下がったり退職者が増えたりするおそれがあります。
ボーナスがない企業は、その分基本給を多めに設定してバランスを取っている傾向にあります。ボーナスを支給しないデメリットをどうカバーするか考える必要があるでしょう。
中小企業のボーナス支給でよくあるトラブル
ここでは中小企業のボーナス支給でよくあるトラブルを3つ紹介します。
一つずつ紹介します。
支給額が少ない
ボーナスの支給額が他の社員に比べて少なくなると不満が生じやすくトラブルに発展する恐れがあります。しかし、同期などと金額の差があっても、就業規則などの支給方法に則った方法で計算されている場合は問題ありあせん
事業の業績や資金繰りなどの影響したり、能力によって変動する可能性があるためです。
しかし、事前に明記されていない理由や特定の人物への嫌がらせ目的で減額された場合には、会社側が違法になる可能性があります。
大幅に減額された
ボーナスの支給が前回よりも減額されることがあります。しかし、こちらも規則の範囲内であれば違法ではありません。
ボーナスの算出は会社の状況や人事評価などから金額が決められます。たとえば、経営状態が悪くなっている場合は状況に合わせて変動するでしょう。
ボーナスの変動に関しても、就業規則などに明記されているため事前に確認するのがおすすめです。
一方、規則で指定されていない方法や直接的に影響のない理由によって大幅なカットを実施した場合は、会社側が違法になります。
ボーナスが支給されない
会社の業績によっては、突然ボーナスの支給をされなくなることがあります。事前にボーナスについて年に2回の支給があると説明を受けていており、支給されないことは違法行為になると考える方も多いですが、法的には問題ありません。
実は、ボーナスは法的に支給を定めているものではないためです。
就業規則などにも、支給がされない場合を記載している場合も多く、会社の経営状況によってはボーナスがなくなることも考えられるでしょう。
中小企業のボーナス額の最適化には人事評価制度の見直しが不可欠
本記事では、ボーナスの種類として「給与連動型」よりも「業績連動型」が主流になりつつあることや、算定方法としてベースを決めた後に社員ごとの金額を決める流れを解説してきました。
中小企業で、ボーナス金額を最適化するには、給与・賞与体系の見直し、およびそれにともなう人事評価制度の改革が不可欠です。「あしたのクラウド」は、クラウド型の人事評価システムで、人事評価や給与・賞与額のシミュレーションなどの機能を一元管理できます。

人事評価に関連したおすすめセミナーのご案内
人事評価の課題を解決するサービス紹介
あしたのチームのサービス
導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
あした式人事評価シート
 あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア
あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア